難しいことを考える必要はないけれどまったく何も考えないというのはあまりよくない。
知るというのも同じ、運動についても同じ。
専門的に、極端にやる必要はまったくないけれど少しはやったほうがいいと思う。
14 .
February
瑣末すぎることだが最近の御時世では……いやどうせ最近に始まったことではないだろう。なんと読むのか、どういう意味なのかわからない単語が多いという。そこで身近な人が(特に学生だが)首を傾げた言葉を少し書いてみる。
『語彙(ごい)』
意味は使用できる単語、といってもいいがあまり正確ではない。
英語ではボキャブラリー(vocabulary)。英単語から見ると話し言葉のほうが元だろうか。
『揶揄(やゆ)』
(比較的地位の高い人を)からかうこと。馬鹿にすること。
『意外/以外』
何故か誤用が多い。予想外な意味での「いがい」は前者。
比較的教育を受けている人間や年長の人も誤用していることがある。ただ、PCに関連すると誤変換のせいであることが多い。
『神道(しんとう)』
読みが危ない。特に学生の場合は神道を「しんどう」と読む可能性が高い。
もっとも「しんどう」とも読んでいる辞書はあるが少ないし別の意味になる可能性がある。
ちなみに、神道用語の祝詞は「のりと」と読むが式典などのお祝いの言葉という意味の祝詞は「しゅくし」と読む。
『承る(うけたまわる)』
何故か読みが危ない。極稀にこの語の前に「受け」とつけてしまう人もいる。一語だけで読みが多いからだろうか。
『伯父/叔父』
誤用が激しい、というよりは学生が知っていたケースを知らない。恐らく人によってはそれこそ瑣末なことかもしれないがカテゴリー的にはあっている。
前者が父母の兄、後者が父母の弟に対して用いられるもの。
ちなみに義兄弟でも同じような区別。
『遵守(じゅんしゅ)』
「そんしゅ」と読む人間がいた。確かに読めそうだが……比較的使用頻度が高いので読みははっきりしたい。
『稲妻(いなづま)』
書きがわからない人が多かった。特に雷と書く人が多い。
由来は稲の実がなる頃に雷が多く、雷が稲を実らせると考えられていたため。やはり瑣末なことかもしれない。
『瑣末(さまつ)』
書いていて気になったので一応。些細(ささい)の「さ」と同じではないことに注意。意味は取るに足らないこと、つまらないこと。英語でいうとTrivial。数学でたまに使われる。(自明な、証明の必要がないこと。例えば公理など)
ちなみに、少し前に「トリビアの泉」というテレビ番組を放送していたと思うがこのトリビアと語源は同じ。
『黒子(くろこ)(ほくろ)』
二重の意味になる言葉、「くろこ」と読む場合は歌舞伎などで黒い服を着て劇の手助けをする人。パペットマペットのウシ君とカエル君の真ん中にいるようないないような人。
後者の意味は説明する必要がない。どちらもこの書き方である。ただ、後者の場合は誤解を避けるためホクロなどと書いたほうが良いとは思う。
『心太・瓊脂(ところてん)』
昔、食堂に入って後輩の学生に読みを聞かれた覚えがある。
読めなくても仕方ないかもしれないし最近は専ら平仮名表記のため問題はない。
『終日(しゅうじつ)』
何故か終日を「一日の終わり」というな意味にとっている人がいたが、意味は「一日中」である。「ひねもす」という読み方もあるがやや古文的。
この言葉は若干曖昧な表現ではある。「○時から終日」という表現もできる。この場合は○時からずっと、という意味だ。
意味は使用できる単語、といってもいいがあまり正確ではない。
英語ではボキャブラリー(vocabulary)。英単語から見ると話し言葉のほうが元だろうか。
『揶揄(やゆ)』
(比較的地位の高い人を)からかうこと。馬鹿にすること。
『意外/以外』
何故か誤用が多い。予想外な意味での「いがい」は前者。
比較的教育を受けている人間や年長の人も誤用していることがある。ただ、PCに関連すると誤変換のせいであることが多い。
『神道(しんとう)』
読みが危ない。特に学生の場合は神道を「しんどう」と読む可能性が高い。
もっとも「しんどう」とも読んでいる辞書はあるが少ないし別の意味になる可能性がある。
ちなみに、神道用語の祝詞は「のりと」と読むが式典などのお祝いの言葉という意味の祝詞は「しゅくし」と読む。
『承る(うけたまわる)』
何故か読みが危ない。極稀にこの語の前に「受け」とつけてしまう人もいる。一語だけで読みが多いからだろうか。
『伯父/叔父』
誤用が激しい、というよりは学生が知っていたケースを知らない。恐らく人によってはそれこそ瑣末なことかもしれないがカテゴリー的にはあっている。
前者が父母の兄、後者が父母の弟に対して用いられるもの。
ちなみに義兄弟でも同じような区別。
『遵守(じゅんしゅ)』
「そんしゅ」と読む人間がいた。確かに読めそうだが……比較的使用頻度が高いので読みははっきりしたい。
『稲妻(いなづま)』
書きがわからない人が多かった。特に雷と書く人が多い。
由来は稲の実がなる頃に雷が多く、雷が稲を実らせると考えられていたため。やはり瑣末なことかもしれない。
『瑣末(さまつ)』
書いていて気になったので一応。些細(ささい)の「さ」と同じではないことに注意。意味は取るに足らないこと、つまらないこと。英語でいうとTrivial。数学でたまに使われる。(自明な、証明の必要がないこと。例えば公理など)
ちなみに、少し前に「トリビアの泉」というテレビ番組を放送していたと思うがこのトリビアと語源は同じ。
『黒子(くろこ)(ほくろ)』
二重の意味になる言葉、「くろこ」と読む場合は歌舞伎などで黒い服を着て劇の手助けをする人。パペットマペットのウシ君とカエル君の真ん中にいるようないないような人。
後者の意味は説明する必要がない。どちらもこの書き方である。ただ、後者の場合は誤解を避けるためホクロなどと書いたほうが良いとは思う。
『心太・瓊脂(ところてん)』
昔、食堂に入って後輩の学生に読みを聞かれた覚えがある。
読めなくても仕方ないかもしれないし最近は専ら平仮名表記のため問題はない。
『終日(しゅうじつ)』
何故か終日を「一日の終わり」というな意味にとっている人がいたが、意味は「一日中」である。「ひねもす」という読み方もあるがやや古文的。
この言葉は若干曖昧な表現ではある。「○時から終日」という表現もできる。この場合は○時からずっと、という意味だ。
PR
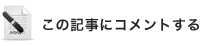
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(03/02)
(03/02)
(02/25)
(02/23)
(02/20)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
鶏冠(とさか)
性別:
男性
趣味:
Civilization3/4、mahjong
ブログ内検索
最古記事
P R
アクセス解析
カウンター
