難しいことを考える必要はないけれどまったく何も考えないというのはあまりよくない。
知るというのも同じ、運動についても同じ。
専門的に、極端にやる必要はまったくないけれど少しはやったほうがいいと思う。
20 .
February
題名でわかりにくい表現を使ってしまったが要するに『子供の「何故勉強するの?」という問いに対して我々はどのように答えるべきなのか』が課題だ。
さて、これは科目別に処理するべきだろう。とりあえずここでは高校生をターゲットにしたい。何故かといえば中学生までの学習で必要性について語るに値するほどの教科はないからだ。義務教育だけあって必要最低限のものだけが入っている。
特に疑問が多いのが「歴史」「数学」「国語」あたりだろう。初めに言っておきたいが国語のうち、古文と漢文については正直にいって実用性(必要性ではない)がわからない。美術や音楽などに類する教養としての認識を持っている。
確かに論語や平家物語などの素晴しい古典はたくさんあるがそれを原文で読む必要がどこにあるのか。原文でなければ読み取れない繊細なニュアンスを感じるほど深く学習できるのかなどの疑問点がある。
念のために言っておくが教養が必要ないといっているわけではない。根本的に要求されている性質が異なることを言っているだけだ。
さて、これは科目別に処理するべきだろう。とりあえずここでは高校生をターゲットにしたい。何故かといえば中学生までの学習で必要性について語るに値するほどの教科はないからだ。義務教育だけあって必要最低限のものだけが入っている。
特に疑問が多いのが「歴史」「数学」「国語」あたりだろう。初めに言っておきたいが国語のうち、古文と漢文については正直にいって実用性(必要性ではない)がわからない。美術や音楽などに類する教養としての認識を持っている。
確かに論語や平家物語などの素晴しい古典はたくさんあるがそれを原文で読む必要がどこにあるのか。原文でなければ読み取れない繊細なニュアンスを感じるほど深く学習できるのかなどの疑問点がある。
念のために言っておくが教養が必要ないといっているわけではない。根本的に要求されている性質が異なることを言っているだけだ。
まず、「歴史」について。これは非常に多くの生徒が突き当たる疑問だと思う。結論から言って少なくとも古代史は教養の部類に入り実学とは言えない。
古代史、もしくは一部の中世史はほぼ知っていれば色々なことに応用が効き見聞が広くなるなどの教養的な利点はあれど直接的に利益に結びつく実学ではない。古代ローマの皇帝の名前を実社会で使用する場面というのはない。しかしながら、現代史ないし近代史については実社会において大いに役立つだろう。
何故ならば近代から現代における流れを知っていなければ国際情勢を理解するのが不可能だからだ。現在起こっていることの原因こそが歴史であり、自分が今存在するルーツを辿るのが祖先の歴史であり大局的には日本史であり世界史だ。
国連の安全保障理事会に何故ドイツや日本が含まれないのかは第二次世界大戦に原因があり、その第二次世界大戦は第一次世界対戦に原因があり、その第一次世界大戦の原因はヨーロッパの植民地戦争、そして大航海時代、イスラームとキリスト教の宗教戦争……といくつもの原因と結果が複雑に絡み合い現代の状況へと歴史は紡がれる。
次に「数学」についてだが……理系でなければ数学IA以上は必要ないと思っている。必要最低限の数学的な知識や思考、確率論などの学習さえしていればそれ以上の課程は文系の学生にとって将来的な実用性はほとんどない。理系であれば数学は非常に汎用性のある分野になるだろう。特に工学系ではベクトルや微積分の扱えない学生がどのようにして工業を営んでいくのか悩むところだ。
「国語」……この場合は現代文だが、どう考えても実学じゃないだろうか。人間が情報を伝達する手段において言語がどれほど大きな役割を果たしているのか態々解説する必要があるのだろうか。
ただ「歴史」「国語」についてはいくつかの点においてカリキュラムを改善する余地は存在すると思っている。まず、歴史については前述した通り現代から通じる脈々とした流れであるため興味を持たせるためにはむしろ現代の情勢から過去へと遡るという授業のほうがよいのではないだろうか。
また、国語の……特に中学校についてだが作文のカリキュラムはどうにかならないだろうか。まず体系的ではないのが疑問だ。小学生の頃に多くの人が作文を書かされた記憶があると思うがその際に教官は「作文のノウハウ」について体系的に教えたことがあるだろうか?一部の優秀な私学校については例外だろうが大抵の場合は「自由に書きなさい」とだけ言われていたと思う。
ちなみに不思議なことだがこの自由というのは大抵の場合、人間の創作を大きく制限する。自由にせよ、といわれたとき人間はむしろ他人を模倣しだす。逆にこういった枠組みのなかで行え、といった制限を加えるとその制限の中で意外なほど個性を発揮する。非常に面白い、天邪鬼(あまのじゃく)な性質だ。
さて、このように何の予備知識もなく自由に書けと言われると途方にくれてしまう生徒が圧倒的に多い。それはそうだ、きちんとした指針や方法論なしにいきなり創作をさせるなんて地図も持たせずに行き場所だけ告げて見知らぬ土地に放り出すのとなんら変わりない。本来ならこういった作業を課す前に作文の定石やどのような手順で書けばよいのかを説明するべきではないか。
具体的に「まず、何を書くかを箇条書きにする」「次に、そこから構成を考える」「自分の経験や考えを…」などのように手順を示せば少しは違うだろう。こういった授業について「なんでも教えないと出来ない子になる」などといった批判が生まれることがあるがそれは誤解というもの。新しいことは古いことの積み重ねの上にこそ生まれるものだ。例えば初めて見た数学の問題でも解けてしまうのは類似したパターンを複数記憶しているためだ。まったく見た来ない形の問題でも何千問ものパターンを解き続けていれば問題に対するアプローチの方法は見つかる。そういうものだと思う。
とはいっても教育の専門家がそうしないということはなんらかの理由があるのだろうか。コストや授業時間に教えることが難しいとか……思うに中学と高校はやや授業に重なる部分が多く冗長に思えるが。今後はむしろこの理由について考えていく。
PR
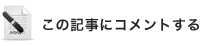
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(03/02)
(03/02)
(02/25)
(02/23)
(02/20)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
鶏冠(とさか)
性別:
男性
趣味:
Civilization3/4、mahjong
ブログ内検索
最古記事
P R
アクセス解析
カウンター
