難しいことを考える必要はないけれどまったく何も考えないというのはあまりよくない。
知るというのも同じ、運動についても同じ。
専門的に、極端にやる必要はまったくないけれど少しはやったほうがいいと思う。
09 .
February
原則としてこのブログでは政治的な話には接触しないようにしているため、これを口火に何かしらの政治的な主張をしようなどとはまったく思っていない。
ただ、官僚とはそもそもなんなのかを知らずに官僚制度についてあれこれと言ったりこれだから官僚はなどと呟くのはやや早まった行為ではないかとだけ言っておきたい。
さて、官僚制(Bureaucracy)とはtech官吏によって解禁される社会制度で首都のコインとハンマーを50%増させr
などとciv4をプレイしたことがない人にはまったくわからない話はさておき、真面目に解説したい。
誤解されることが多いが官僚制は政治・軍事・行政問わず様々な組織で採用されている。官僚制とは一言で言えば「トップが1人で、上下に階級があり、命令系統がはっきりしている組織制度」である。
ただ、官僚とはそもそもなんなのかを知らずに官僚制度についてあれこれと言ったりこれだから官僚はなどと呟くのはやや早まった行為ではないかとだけ言っておきたい。
さて、官僚制(Bureaucracy)とはtech官吏によって解禁される社会制度で首都のコインとハンマーを50%増させr
などとciv4をプレイしたことがない人にはまったくわからない話はさておき、真面目に解説したい。
誤解されることが多いが官僚制は政治・軍事・行政問わず様々な組織で採用されている。官僚制とは一言で言えば「トップが1人で、上下に階級があり、命令系統がはっきりしている組織制度」である。
特にそれが顕著なのが軍隊や警察などの組織で、これらの組織が的確に素早く一糸乱れぬ行動をするにははっきりした指揮系統と厳密な階級が必要となるため。
組織が大きくなればなるほどまとめるためには官僚制の必要性が如実に表れる。
また、厳密には「家産官僚制」と「近代官僚制」が社会学者ウェーバーによって定義されているが前者は現代ではほとんど用いられない、というか現代において官僚といえば後者であるため省く。
官僚制の主な特徴は
・形式的で恒常的な規則に基づいて運営される。
・上意下達の指揮命令系統を持つ。
・一定の資格・資質を持った者を採用し、組織への貢献度に応じて地位、報償が与えられる。
・職務が専門的に分化され、各セクションが協力して組織を運営していく分業の形態をとる。
(引用:wikipedia該当項目)
特に説明は不要だと思うが最後の行については補足。
職務を専門的に細分化するというのは素早く正確に組織的な業務を行う上では必要不可欠な制度だというのを分かって欲しい。
このような分業制は近代の組織では必ず存在するものであり、工場のライン生産なども同じ原理で行われている。
企業で例えれば業務の専門化がない状況というのは100人の社員全員が営業・経理・総務・生産・経営などを一人一人が行っている状況である。つまり、自分で企画し自分で予算を決め自分で売るという状態。 もちろん、業務を覚えるのにはかなりの年月がかかる上に仮に覚えたとしてもその業務だけをやり続けてきた人間と比べればそれぞれの仕事の質は圧倒的に落ちる。
その前の業務に関してもそうだがたまに勘違いしている人間がいるのではっきり書けば能力のある人間を雇用する場合はそれに見合うだけの名誉・給与・福利が必要であり逆に言えばそれらに見合うだけの人間しか雇用できない。
公務員の平均収入と企業のそれを比べるなんてことはまるで無意味且つ印象操作の臭いさえある。能力と労働量別に見ればむしろ安いし、それでも人が集まるのは公務員の安定性と福利厚生の魅力だ。
さて、このように非常に合理的に見える官僚制だが社会学者マートンによっていくつかの欠点、官僚制の逆機能と呼ばれるものが発見された。
・規則万能(例:規則に無いから出来ないという杓子定規の対応)
・権威主義的傾向(例:役所窓口などでの冷淡で横柄な対応)
・繁文縟礼(はんぶんじょくれい)(例:膨大な処理済文書の保管を専門とする部署が存在すること)
・セクショナリズム(例:縦割り政治や専門外の業務を避けようとするなどの閉鎖的傾向)
などが主である。一部引用は前回と同じくwikipediaから。
念のために言っておくがこれは官僚制全般における欠点であり、別に日本の官僚だからというわけではないことを知っておいて頂きたい。いわば官僚制のデメリットである。
特に問題になりがちなのがセクショナリズムと法規(規則)万能主義である。だが、考えてみれば仕方のないというか当然の結果といったことであることがわかる。
命令系統を一本にしてそれを絶対の物とすれば権威主義になり、規則を守るように徹底すれば規則万能となる。
専門化や業務の分化を進めるとセクショナリズムに傾倒することになる。メリットの弊害からデメリットは生まれる。
また、現在の日本における官僚制の問題は官僚制そのものにあるというよりはむしろそれを扱う側である政治サイドに問題があるとも言える。
そもそも官僚制は政治を行わせるために発明された社会制度ではなくあくまでも政治家や指導者によって決められた指針に従って正確で素早い作業や処理を行うためのものである。
官僚に政治を任せるというのは機械に機械が何をするべきか考えさせるのと大差ない。とはいっても官僚制に変わる巨大な組織を運営するための社会制度はまだ発明されていない以上多少問題があろうと官僚制を差し替えるというのは非現実的な話だ。
組織が大きくなればなるほどまとめるためには官僚制の必要性が如実に表れる。
また、厳密には「家産官僚制」と「近代官僚制」が社会学者ウェーバーによって定義されているが前者は現代ではほとんど用いられない、というか現代において官僚といえば後者であるため省く。
官僚制の主な特徴は
・形式的で恒常的な規則に基づいて運営される。
・上意下達の指揮命令系統を持つ。
・一定の資格・資質を持った者を採用し、組織への貢献度に応じて地位、報償が与えられる。
・職務が専門的に分化され、各セクションが協力して組織を運営していく分業の形態をとる。
(引用:wikipedia該当項目)
特に説明は不要だと思うが最後の行については補足。
職務を専門的に細分化するというのは素早く正確に組織的な業務を行う上では必要不可欠な制度だというのを分かって欲しい。
このような分業制は近代の組織では必ず存在するものであり、工場のライン生産なども同じ原理で行われている。
企業で例えれば業務の専門化がない状況というのは100人の社員全員が営業・経理・総務・生産・経営などを一人一人が行っている状況である。つまり、自分で企画し自分で予算を決め自分で売るという状態。 もちろん、業務を覚えるのにはかなりの年月がかかる上に仮に覚えたとしてもその業務だけをやり続けてきた人間と比べればそれぞれの仕事の質は圧倒的に落ちる。
その前の業務に関してもそうだがたまに勘違いしている人間がいるのではっきり書けば能力のある人間を雇用する場合はそれに見合うだけの名誉・給与・福利が必要であり逆に言えばそれらに見合うだけの人間しか雇用できない。
公務員の平均収入と企業のそれを比べるなんてことはまるで無意味且つ印象操作の臭いさえある。能力と労働量別に見ればむしろ安いし、それでも人が集まるのは公務員の安定性と福利厚生の魅力だ。
さて、このように非常に合理的に見える官僚制だが社会学者マートンによっていくつかの欠点、官僚制の逆機能と呼ばれるものが発見された。
・規則万能(例:規則に無いから出来ないという杓子定規の対応)
・権威主義的傾向(例:役所窓口などでの冷淡で横柄な対応)
・繁文縟礼(はんぶんじょくれい)(例:膨大な処理済文書の保管を専門とする部署が存在すること)
・セクショナリズム(例:縦割り政治や専門外の業務を避けようとするなどの閉鎖的傾向)
などが主である。一部引用は前回と同じくwikipediaから。
念のために言っておくがこれは官僚制全般における欠点であり、別に日本の官僚だからというわけではないことを知っておいて頂きたい。いわば官僚制のデメリットである。
特に問題になりがちなのがセクショナリズムと法規(規則)万能主義である。だが、考えてみれば仕方のないというか当然の結果といったことであることがわかる。
命令系統を一本にしてそれを絶対の物とすれば権威主義になり、規則を守るように徹底すれば規則万能となる。
専門化や業務の分化を進めるとセクショナリズムに傾倒することになる。メリットの弊害からデメリットは生まれる。
また、現在の日本における官僚制の問題は官僚制そのものにあるというよりはむしろそれを扱う側である政治サイドに問題があるとも言える。
そもそも官僚制は政治を行わせるために発明された社会制度ではなくあくまでも政治家や指導者によって決められた指針に従って正確で素早い作業や処理を行うためのものである。
官僚に政治を任せるというのは機械に機械が何をするべきか考えさせるのと大差ない。とはいっても官僚制に変わる巨大な組織を運営するための社会制度はまだ発明されていない以上多少問題があろうと官僚制を差し替えるというのは非現実的な話だ。
PR
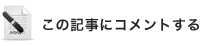
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(03/02)
(03/02)
(02/25)
(02/23)
(02/20)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
鶏冠(とさか)
性別:
男性
趣味:
Civilization3/4、mahjong
ブログ内検索
最古記事
P R
アクセス解析
カウンター
