難しいことを考える必要はないけれどまったく何も考えないというのはあまりよくない。
知るというのも同じ、運動についても同じ。
専門的に、極端にやる必要はまったくないけれど少しはやったほうがいいと思う。
02 .
March
話はまったく関係ないが走る・歩く・立つという基本的な行動も本能ではなく学習によるものらしい。つまり、泳ぐとか字を読むのように後天的にトレーニングして行えるようになることのようだ。そのため、誰かに立つことを訓練してもらったり誰かが立っているのを見て自分も真似しようとしないとできない。このため、非常事態に陥って取り乱すと稀に脳から知識が零れ落ち上手く立ち上がったり歩いたりできなくなる。それでも原始的な行動である呼吸などはできる。これは先天的な行動なのだろう。
何故、無関係の話に飛んだのかというと何故か多くの人は文章というのが技術であるということを認識しておらず文章が書けないのはきちんとした訓練を受けていないせいなのに自分に才能がないからだと勘違いしているためだ。文章にしても絵を描くにしても走ることさえもきちんとした訓練や教育を受ければ9割がたはなんとかなるものだが、そういった機会に恵まれる人は少ない。機会さえあれば自分から進んで飛び込むことをお勧めしたい。
何故、無関係の話に飛んだのかというと何故か多くの人は文章というのが技術であるということを認識しておらず文章が書けないのはきちんとした訓練を受けていないせいなのに自分に才能がないからだと勘違いしているためだ。文章にしても絵を描くにしても走ることさえもきちんとした訓練や教育を受ければ9割がたはなんとかなるものだが、そういった機会に恵まれる人は少ない。機会さえあれば自分から進んで飛び込むことをお勧めしたい。
さて、肝心のストーリーの作り方についてだがこの場合は小説という形態を前提にして話を進めさせてもらう。まず最初に自分が書きたい主題を用意する。分かりにくいと思うので実際の小説から題材を逆抜きしてみよう。
太宰 治は御存知の方が多いと思う、多分この作家は読む作品によって持つ印象が変わると思う。具体的には走れメロス・斜陽・人間失格あたりが代表作だ。どの作品も名作だと思うが特に斜陽は精読をお勧めする。これらの作品について主題を考えてみよう。
まず、『走れメロス』だがこれは非常に有名な作品であるし確か低級学生の教科書にも載っているはずだ。それに主題もわかりやすくはっきりしている実にいいサンプルだと思う。
最初に思いつくのは『人は人を信頼する生き物だ』というようなことだろうか。
ただ、もう少し深く読み込めば本当に正しいのはメロス達なのかそれとも猜疑心の塊だった王なのかという疑問が浮かぶかもしれない。実直な羊飼いであるメロスにとって人を疑うというのは恥で悪徳だというのはわかる。しかし、その実直さを王に要求していいのだろうか。ある意味ではこの要求というのは傲慢にも思える。もしかしたら王は実際に命を狙われることも度々あったかもしれない。実際、主人公のメロス自身に冒頭から暗殺されそうになっていた。その権力を奪おうとする人間がいないと断言は出来ない。疑うということが王にとって生きるのに必要な行為だったかもしれない、そうでなければ裸の王様のように笑いものになるだろう。『おまえには、わしの孤独がわからぬ』という王の一言がそれを象徴している。
それに付け加えて川を越えたところで現れた山賊たちに対してメロスはなんと言っただろうか。『さては、王の命令で、ここで私を待ち伏せしていたのだな』あれほど疑うことは悪徳だなどと言い、それを証明することに命をかけておきながら王を当然のように疑っている。実際のところ、この山賊が王の命令だと明記はされていない。まあ、『その、いのちが欲しいのだ』といっているのでそう思うのが当然だが。
また、文中の最後で言われている通りメロス達はお互いをわずかながらも疑う気持ちがあったことを話している。ここから思うに……「疑念というのは誰にでも生ずる」という隠れた主題が存在することにも気づくだろう。
太宰 治は御存知の方が多いと思う、多分この作家は読む作品によって持つ印象が変わると思う。具体的には走れメロス・斜陽・人間失格あたりが代表作だ。どの作品も名作だと思うが特に斜陽は精読をお勧めする。これらの作品について主題を考えてみよう。
まず、『走れメロス』だがこれは非常に有名な作品であるし確か低級学生の教科書にも載っているはずだ。それに主題もわかりやすくはっきりしている実にいいサンプルだと思う。
最初に思いつくのは『人は人を信頼する生き物だ』というようなことだろうか。
ただ、もう少し深く読み込めば本当に正しいのはメロス達なのかそれとも猜疑心の塊だった王なのかという疑問が浮かぶかもしれない。実直な羊飼いであるメロスにとって人を疑うというのは恥で悪徳だというのはわかる。しかし、その実直さを王に要求していいのだろうか。ある意味ではこの要求というのは傲慢にも思える。もしかしたら王は実際に命を狙われることも度々あったかもしれない。実際、主人公のメロス自身に冒頭から暗殺されそうになっていた。その権力を奪おうとする人間がいないと断言は出来ない。疑うということが王にとって生きるのに必要な行為だったかもしれない、そうでなければ裸の王様のように笑いものになるだろう。『おまえには、わしの孤独がわからぬ』という王の一言がそれを象徴している。
それに付け加えて川を越えたところで現れた山賊たちに対してメロスはなんと言っただろうか。『さては、王の命令で、ここで私を待ち伏せしていたのだな』あれほど疑うことは悪徳だなどと言い、それを証明することに命をかけておきながら王を当然のように疑っている。実際のところ、この山賊が王の命令だと明記はされていない。まあ、『その、いのちが欲しいのだ』といっているのでそう思うのが当然だが。
また、文中の最後で言われている通りメロス達はお互いをわずかながらも疑う気持ちがあったことを話している。ここから思うに……「疑念というのは誰にでも生ずる」という隠れた主題が存在することにも気づくだろう。
PR
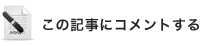
| HOME | 作文の初歩的な定石、序文の書き方
>>
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(03/02)
(03/02)
(02/25)
(02/23)
(02/20)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
鶏冠(とさか)
性別:
男性
趣味:
Civilization3/4、mahjong
ブログ内検索
最古記事
P R
アクセス解析
カウンター
