難しいことを考える必要はないけれどまったく何も考えないというのはあまりよくない。
知るというのも同じ、運動についても同じ。
専門的に、極端にやる必要はまったくないけれど少しはやったほうがいいと思う。
02 .
March
作文を書く際には、まず初めに与えられた課題(ex.税金、人権)について何か一つ伝えたいこと(意見)を考える。例で言えば「税金」という課題について「税金の効果的に使うべきだ」、「挑戦」という課題に対して「挑戦は周囲からの理解や協力が必要だ」など。
こういった意見を読者に対して説得力を持って伝えるためにそう思う根拠や実際の体験談などを付け加える。この根拠と結論の二つで構成する方法が単純でわかりやすく小中学生の場合は基本的にこれでよい。大学生や社会人になると単に自分の意見を述べるだけでなく問題点・現状分析・解決策などを論理的に説明する必要があるため、これより複雑な序論・本論・結論という様に分ける三部構成や起承転結のような四部構成が用いられる。
こういった意見を読者に対して説得力を持って伝えるためにそう思う根拠や実際の体験談などを付け加える。この根拠と結論の二つで構成する方法が単純でわかりやすく小中学生の場合は基本的にこれでよい。大学生や社会人になると単に自分の意見を述べるだけでなく問題点・現状分析・解決策などを論理的に説明する必要があるため、これより複雑な序論・本論・結論という様に分ける三部構成や起承転結のような四部構成が用いられる。
【序文の書き方】
まず序文の書き方はいくつかある。比較的多いのが『最初から結論を述べる』書き方でこのような方法をアンチ・クライマックス法といったりもする。この方法の魅力は構成を考えるのが容易いことである、『~だと思う、何故ならば~だからだ』という非常に明快な論理構成になり途中で自分が何を言いたいのかわからなくなることが少ない。
また、読者の興味を惹きつける書き方として『非常識なことを書く』『意外な事実や出来事から始める』などがある。前者の場合は「図書館は必要ではない」などと非常識的な書き始めをするタイプで、惹きつける効果こそあるものの最終的な結論がネガティブになりがちなため扱いにくい。
後者の場合は「普段物静かな上司が突然怒鳴った」など非日常的な出来事などを書き、その原因や過程から本論へと話を繋げる方法で構成が難しいものの前者ほど扱いは難しくはない。
そして、あまりお勧めはしないが『格言・名言の引用で始める』というパターンもある。例えば福沢諭吉の著作・学問のすゝめに書かれた序文のような書き出しだ。
天は人の上に人を造らず,人の下に人を造らずと云えり。されば天より人を生ずるには,万人は万人皆同じ位にして,生れながら貴賤上下の差別なく,万物の霊たる身と心との働を以て,天地の間にあるよろずの物を資り,以て衣食住の用を達し,自由自在,互に人の妨をなさずして,各安楽にこの世を渡らしめ給うの趣意なり。 されども今広くこの人間世界を見渡すに,かしこき人あり,おろかなる人あり,貧しきもあり,富めるもあり,貴人もあり,下人もありて,その有様雲と泥との相違あるに似たるは何ぞや。その次第甚だ明なり。実語教に,人学ばざれば智なし,智なき者は愚人なりとあり。されば賢人と愚人との別は,学ぶと学ばざるとに由て出来るものなり。
斜線部は学問のすゝめ 初編からの引用。
この文章は非常に良い作文例だといえる。まず最初に『天は人の上に人を造らず,人の下に人を造らずと云えり』と格言を引用して書き始め(云えり、というのは現代語で「言われている」の意)、その後に『されども今広くこの人間世界を見渡すに,かしこき人あり,おろかなる人あり』と格言を否定・懐疑する文章へとつなげている。(されども、は現代語で「しかし」の意)
学問のすすめの始めではこのような格言を引用した問題提起をし、その疑問に対して「このような不平等は学問によって決まる。だから平等になるためには学問をするべきだ」という現状分析と解決策を提示している。(ちなみに上の格言はアメリカ合衆国の独立宣言から。原文は"all Men are created equal")
まず序文の書き方はいくつかある。比較的多いのが『最初から結論を述べる』書き方でこのような方法をアンチ・クライマックス法といったりもする。この方法の魅力は構成を考えるのが容易いことである、『~だと思う、何故ならば~だからだ』という非常に明快な論理構成になり途中で自分が何を言いたいのかわからなくなることが少ない。
また、読者の興味を惹きつける書き方として『非常識なことを書く』『意外な事実や出来事から始める』などがある。前者の場合は「図書館は必要ではない」などと非常識的な書き始めをするタイプで、惹きつける効果こそあるものの最終的な結論がネガティブになりがちなため扱いにくい。
後者の場合は「普段物静かな上司が突然怒鳴った」など非日常的な出来事などを書き、その原因や過程から本論へと話を繋げる方法で構成が難しいものの前者ほど扱いは難しくはない。
そして、あまりお勧めはしないが『格言・名言の引用で始める』というパターンもある。例えば福沢諭吉の著作・学問のすゝめに書かれた序文のような書き出しだ。
天は人の上に人を造らず,人の下に人を造らずと云えり。されば天より人を生ずるには,万人は万人皆同じ位にして,生れながら貴賤上下の差別なく,万物の霊たる身と心との働を以て,天地の間にあるよろずの物を資り,以て衣食住の用を達し,自由自在,互に人の妨をなさずして,各安楽にこの世を渡らしめ給うの趣意なり。 されども今広くこの人間世界を見渡すに,かしこき人あり,おろかなる人あり,貧しきもあり,富めるもあり,貴人もあり,下人もありて,その有様雲と泥との相違あるに似たるは何ぞや。その次第甚だ明なり。実語教に,人学ばざれば智なし,智なき者は愚人なりとあり。されば賢人と愚人との別は,学ぶと学ばざるとに由て出来るものなり。
斜線部は学問のすゝめ 初編からの引用。
この文章は非常に良い作文例だといえる。まず最初に『天は人の上に人を造らず,人の下に人を造らずと云えり』と格言を引用して書き始め(云えり、というのは現代語で「言われている」の意)、その後に『されども今広くこの人間世界を見渡すに,かしこき人あり,おろかなる人あり』と格言を否定・懐疑する文章へとつなげている。(されども、は現代語で「しかし」の意)
学問のすすめの始めではこのような格言を引用した問題提起をし、その疑問に対して「このような不平等は学問によって決まる。だから平等になるためには学問をするべきだ」という現状分析と解決策を提示している。(ちなみに上の格言はアメリカ合衆国の独立宣言から。原文は"all Men are created equal")
PR
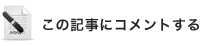
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(03/02)
(03/02)
(02/25)
(02/23)
(02/20)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
鶏冠(とさか)
性別:
男性
趣味:
Civilization3/4、mahjong
ブログ内検索
最古記事
P R
アクセス解析
カウンター
