難しいことを考える必要はないけれどまったく何も考えないというのはあまりよくない。
知るというのも同じ、運動についても同じ。
専門的に、極端にやる必要はまったくないけれど少しはやったほうがいいと思う。
09 .
February
『雄弁は銀、沈黙は金(Speech is silver, Silence is golden)』
単純な知識の伝達という意味で誰かに何かを話す、ということならとても簡単なことでしかも重要なこと。
もちろん、それを正確に素早く伝えるのは技術のいることだけれど。
単純な知識の伝達という意味で誰かに何かを話す、ということならとても簡単なことでしかも重要なこと。
もちろん、それを正確に素早く伝えるのは技術のいることだけれど。
『わずかなる知識しか持たぬ人間は多く語る。識者は多く黙っている』
などと社会学者ルソーは言っているし他にも多くの人々が賢い人ほど何も言わないものだと言っている。しかしそれが常に正しいだろうか。自分はこの言葉に多少の疑問がある。
これは識者の性質を客観的に見て言っているのだろうか、それとも識者ならこうあるべきという姿を主観的に言っているのだろうか。素直に読めば前者だろうが、なら識者はどうあるべきだろうか。
人間というのは何かしらの知識を得たときそれを誰か他人に話したくてうずうずしてしまう性質がある。それ自体は自然なもので理にかなった性質だと思う。
何故ならば人間が何かしらの経験や知識を誰かに話したいと思う気持ちがもしもなかったとすれば社会として大きな不利益が生じるからだ。
例えばある人が自分の経験から特定の魚に毒があることを知った時、その人が瑣末なことでも他人に話したい欲望がなければ誰にも話さないまま死ぬまで自分だけの知識にしておくだろう。
ただしそういった知識の独占が有利に働くこともある。
例えばこの人がそういった魚の判別に関わる仕事をしている場合なら彼の業務分野を独占する意味で誰にも話さないことは理的かもしれない。
しかし、それは個人の利益であって全体の利益にはならない。
魚の毒についての知識を誰かに話せばその誰かも他の誰かに話したくなる。もしくは記録して誰かに読んでもらいたくなる。
そういった知識の伝達・共有化が行われればその魚を誤って食べて死んでしまう人は減少するだろう。
もちろん、既にそれを知っている人からは「そんな知識を偉そうに」と反感を買ってしまうだろうしその結果として上に書いたような言葉が言われるのかもしれない。
しかしそれなら、きちんと知っている人が正確に情報を伝えるべきだ。識者が多くを黙っていては困る。むしろ積極的に教授して欲しい。
また、これも人間が持つ一種の性質だが他人に何かを説明するとその知識について理解や記憶がより深まる。
逆に言えばその知識について十分相手が納得するような説明が出来れば自分自身がそれについて理解していることも再確認できる。
例えば学生なら自分で学習した数学の解法や英語の文法問題などを誰かに説明を聞いてもらったほうがよい。自分の記憶の整理にもなるし、相手にとって未知の知識なら俺に良しお前に良しの幸せ連鎖反応になる。こうした作業によってノートをいじましく書くよりもよほど体系的に学習内容のまとめができるだろう。
結論を言えば、自分は「人が知識を誰かに話したいと思うのは恥ずかしいことではないし、むしろ積極的に話したほうがよいということ」を言いたい。
ただ、そのときの注意点としてあやふやな情報や誤った知識を確実な情報のように装飾して話してしまわないように気をつけて欲しい。
もしも、なんらかの知識を書き記したり伝えたりするときにはできるだけその情報源(ソース元)や信頼性(自分の経験か、他人の伝聞かなど)を一緒にして欲しい。
こういったことに注意してさえいれば知識の共有はとても素晴しいもので多少のデメリットを考えても余りあるほどの利益がある。こういった思想の元にwikipediaが設立されたのは有名な話であり、自分もその考えには共感している。
だから、何か新しいことを覚えたときには誰かに話を聞いてもらおう。もちろん、話してあげるのではなく聞いてもらうといった程度に考えておくことが必要だし、相手が明らかに興味を持っていなければやめておくに越したことはないけれど。
最初に書いた言葉を思い出して欲しい。
『雄弁は銀、沈黙は金』と言われている。
確かに沈黙は必要だし重要でもあるが、だからといって雄弁が必要ないわけではない。沈黙と雄弁は時と場合を考えて使い分けよう。
そして、金だけでも銀だけでもなく金銀どちらも手に入れよう。
などと社会学者ルソーは言っているし他にも多くの人々が賢い人ほど何も言わないものだと言っている。しかしそれが常に正しいだろうか。自分はこの言葉に多少の疑問がある。
これは識者の性質を客観的に見て言っているのだろうか、それとも識者ならこうあるべきという姿を主観的に言っているのだろうか。素直に読めば前者だろうが、なら識者はどうあるべきだろうか。
人間というのは何かしらの知識を得たときそれを誰か他人に話したくてうずうずしてしまう性質がある。それ自体は自然なもので理にかなった性質だと思う。
何故ならば人間が何かしらの経験や知識を誰かに話したいと思う気持ちがもしもなかったとすれば社会として大きな不利益が生じるからだ。
例えばある人が自分の経験から特定の魚に毒があることを知った時、その人が瑣末なことでも他人に話したい欲望がなければ誰にも話さないまま死ぬまで自分だけの知識にしておくだろう。
ただしそういった知識の独占が有利に働くこともある。
例えばこの人がそういった魚の判別に関わる仕事をしている場合なら彼の業務分野を独占する意味で誰にも話さないことは理的かもしれない。
しかし、それは個人の利益であって全体の利益にはならない。
魚の毒についての知識を誰かに話せばその誰かも他の誰かに話したくなる。もしくは記録して誰かに読んでもらいたくなる。
そういった知識の伝達・共有化が行われればその魚を誤って食べて死んでしまう人は減少するだろう。
もちろん、既にそれを知っている人からは「そんな知識を偉そうに」と反感を買ってしまうだろうしその結果として上に書いたような言葉が言われるのかもしれない。
しかしそれなら、きちんと知っている人が正確に情報を伝えるべきだ。識者が多くを黙っていては困る。むしろ積極的に教授して欲しい。
また、これも人間が持つ一種の性質だが他人に何かを説明するとその知識について理解や記憶がより深まる。
逆に言えばその知識について十分相手が納得するような説明が出来れば自分自身がそれについて理解していることも再確認できる。
例えば学生なら自分で学習した数学の解法や英語の文法問題などを誰かに説明を聞いてもらったほうがよい。自分の記憶の整理にもなるし、相手にとって未知の知識なら俺に良しお前に良しの幸せ連鎖反応になる。こうした作業によってノートをいじましく書くよりもよほど体系的に学習内容のまとめができるだろう。
結論を言えば、自分は「人が知識を誰かに話したいと思うのは恥ずかしいことではないし、むしろ積極的に話したほうがよいということ」を言いたい。
ただ、そのときの注意点としてあやふやな情報や誤った知識を確実な情報のように装飾して話してしまわないように気をつけて欲しい。
もしも、なんらかの知識を書き記したり伝えたりするときにはできるだけその情報源(ソース元)や信頼性(自分の経験か、他人の伝聞かなど)を一緒にして欲しい。
こういったことに注意してさえいれば知識の共有はとても素晴しいもので多少のデメリットを考えても余りあるほどの利益がある。こういった思想の元にwikipediaが設立されたのは有名な話であり、自分もその考えには共感している。
だから、何か新しいことを覚えたときには誰かに話を聞いてもらおう。もちろん、話してあげるのではなく聞いてもらうといった程度に考えておくことが必要だし、相手が明らかに興味を持っていなければやめておくに越したことはないけれど。
最初に書いた言葉を思い出して欲しい。
『雄弁は銀、沈黙は金』と言われている。
確かに沈黙は必要だし重要でもあるが、だからといって雄弁が必要ないわけではない。沈黙と雄弁は時と場合を考えて使い分けよう。
そして、金だけでも銀だけでもなく金銀どちらも手に入れよう。
PR
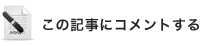
<<
危機管理についての教育
| HOME |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(03/02)
(03/02)
(02/25)
(02/23)
(02/20)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
鶏冠(とさか)
性別:
男性
趣味:
Civilization3/4、mahjong
ブログ内検索
最古記事
P R
アクセス解析
カウンター
