難しいことを考える必要はないけれどまったく何も考えないというのはあまりよくない。
知るというのも同じ、運動についても同じ。
専門的に、極端にやる必要はまったくないけれど少しはやったほうがいいと思う。
09 .
February
『危機管理』とは
テロ、事件、事故又は災害などの不測の事態に対して、被害を最小限にするための手段。(危機管理とは:はてなキーワード)
ホーム転落 救助の連携プレー 東京消防庁 親子らに感謝状
2009年1月21日
東京消防庁の滝野川消防署は二十日、北区のJR尾久駅でホームから転落した男性会社員(32)を素早く救助したとして、荒川区の高校三年天野貴博さん(18)と弟の中学三年智博さん(15)、母理香さん(46)に感謝状を贈った。JR東日本によると、約三分後には上野発高崎行き普通電車が進入する予定だった。
同消防署によると、十八日午後九時半ごろ、ホームを歩いていた男性が看板にぶつかり転落。理香さんが駅員を呼びに行く一方、貴博さんが別の男性二人と飛び降り、ホーム上の智博さんと大学生二人が助け上げた。転落の男性は頭に軽いけが。
この間、別の女性が非常停止ボタンを押して電車を止めた。救助に当たったのは計八人で、同署はほかの五人にも感謝状を贈る方針。貴博さんは「目の前で落ちた人をぜひ助けたいと思った」と話しているという。
(東京新聞:http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20090121/CK2009012102000082.html)
人を助けようとする気持ちはとても素晴しいが彼らには消防庁から感謝状の他に適切な指導も必要な気がするのだが気のせいだろうか。
テロ、事件、事故又は災害などの不測の事態に対して、被害を最小限にするための手段。(危機管理とは:はてなキーワード)
ホーム転落 救助の連携プレー 東京消防庁 親子らに感謝状
2009年1月21日
東京消防庁の滝野川消防署は二十日、北区のJR尾久駅でホームから転落した男性会社員(32)を素早く救助したとして、荒川区の高校三年天野貴博さん(18)と弟の中学三年智博さん(15)、母理香さん(46)に感謝状を贈った。JR東日本によると、約三分後には上野発高崎行き普通電車が進入する予定だった。
同消防署によると、十八日午後九時半ごろ、ホームを歩いていた男性が看板にぶつかり転落。理香さんが駅員を呼びに行く一方、貴博さんが別の男性二人と飛び降り、ホーム上の智博さんと大学生二人が助け上げた。転落の男性は頭に軽いけが。
この間、別の女性が非常停止ボタンを押して電車を止めた。救助に当たったのは計八人で、同署はほかの五人にも感謝状を贈る方針。貴博さんは「目の前で落ちた人をぜひ助けたいと思った」と話しているという。
(東京新聞:http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20090121/CK2009012102000082.html)
人を助けようとする気持ちはとても素晴しいが彼らには消防庁から感謝状の他に適切な指導も必要な気がするのだが気のせいだろうか。
別に救助にあたった人たちを避難するつもりはないのだが、この場で適切で且つ効果的な判断をしたのは非常停止ボタンを押した女性だろう。
これは結果論でもなんでもなく最善手と言い切れる。理由は言うまでもなく二次災害の防止である。これに類似する事例はいくつもある、いわゆる善意や勇気が裏目に出るケースだ。
消防員が止めるのも聞かずに火災現場に救助しにいき消防員の手間を増やし救助を妨害してしまったり、池で溺れている人を助けようとして何故か自分も池に飛びこみ誰にも連絡されず死亡したり、せっかく岩清水八幡宮へ参拝しに行ったのに山までは行かずに帰ってきてしまったり。
さて、こういった悲劇が何故起こるかといえば適切な知識を有していないことが原因といえよう。
そこで今回は我々のような一般人が事故現場に居合わせた場合の適切な処置を出来るだけ最小限に圧縮して覚えておきたい。
色々な手順を書いても焦ったときに思い出せるかどうかは果てしなく疑問だ、できれば暇なときは自分が妄想の中で大活躍する話を想像して脳内物質を分泌するよりも、自分がこの場で何らかの事故が起こった場合どのように対処すればいいかをシミュレートしていた方が役に立つだろう。
まず最初にすべての事故に共通して言えること。
『周囲の安全を確認する』
重要なことなので滅多に使わないだろう色彩字を使って表現しました。
いの一番にこれを行ってください。じゃないと
『感電している人を助けようとして近づいたために自分も感電する』
『有害ガスを吸って倒れている人を助けようとして自分も(ry』
『毒へビに咬まれた人を助けようとして(ry』
『崖崩れで負傷した人を助けようとして(ry』
『道路の真ん中で倒れている人を(ry』
などなどこれを怠ったばかりに相手を助ける前に自分も要救助者になってしまったり死亡者の数を一つ増やすことになるので絶対に行ってください。
原則として要救助者を助けることよりもこれ以上要救助者を増やさないことです。
危ないと思って無我夢中で、というのはやらないでください。
よくニュースでこのような受け答えをする人がいますができるだけ避けるべきです。まずは冷静になって状況を把握しましょう。
『専門家に連絡する』
これも重要です。まずは自分でどうこうしようなどと考えずに年長者や経験者、特に消防や救助の方に連絡しましょう。自分ひとりしかいない場合なんて滅多にありません。
学校ならば教官に、職場ならば上司に、道端なら周囲の人に、そして救急車を呼びましょう。
工場や職場などではそこを担当している管理者は少なくとも貴方よりは適切な処置を事前に教習しているはずです。まずは連絡しましょう。どうせ1人ではできることはあまりありませんし何度も言いますが危険です。
あとその現場責任者や専門家の指示には絶対従ってください。言い合ってる間にも救助を待っています、
ところで、割と重要なことですが通報する際にどこにどう連絡すればよいか知っていますか?念のために確認しておきましょう。多分5割くらいの人間が知りません。
まず最初に「119」にダイヤルしましょう。
119です、これくらいは覚えて置いてください。
できれば携帯電話に登録しておいてください、そういえばこういった機能が付いた携帯はあるんでしょうか。念のために言っておきますがここで火事だ救急だと悩む必要はありません。とりあえず事故なら119です。
ダイヤルするとオペレーターが「火事ですか?救急ですか?」と尋ねてくるので答えてください。あとは多少慌てていてもオペレーターの質問や指示に冷静になって応えていれば大丈夫です。安心してください、餅は餅屋に、指示はオペレーターに。
言っておかなければならない連絡事項としては
・事故火災の住所(県名から言ってください。出来るだけ詳細に)
・怪我人病人の状態(どうやって怪我したか、現場の状況、症状や出血など)
・現場の目印になる建物など
・通報する人の名前
・救急車の来る場所
などです。念のために言っておきますが、正確に状況を伝えてください。主観で「○○だと思うのですが」などと言わなくていいです。
また、電話は相手が切るまではアクティブにしておいてください。もしかすると追加で指示があるかもしれません。
通報に使用した電話はすぐに出られる位置にいてください。また他の用途には使わず他への連絡は違う端末を使ってください。
あとは、救急車が近くまで来たら現場まで誘導する人を出してください。夜間なら照明を持っていくとGJです。
もしかすると症状によっては嘔吐物を調べる場合があるので可能ならばビニール袋などに保管しましょう。
最低でも1人は事情を知っている人が救急車に同乗することになります。
毒虫などによる場合はその毒虫を可能なら捕獲しましょう。
危険ならば写真を撮るか特徴を観察してください。
あとで血清を入れる際に特定しやすくなります。
(参考:東京消防署公式サイト)
これでも心配なら携帯で『通報マニュアル』と検索して出てきたページをブックマークしておきましょう。マニュアルは最善手です。
というわけでこの二つだけは覚えておきましょう。
もはや、覚えるとかそういうレベルじゃないですけどね。
『安全確認』と『通報』だけ覚えておけばなんとかなります。
下手に処置するよりもずっとファインプレーです。どうせ具体的に何かしなければいけないことがあってもオペレーターの人が教えてくれるはずです。
マニュアル通りの対応もできない人に柔軟な対応なんて無理です。
何故この記事を教育カテゴリで書いたのか。
それはこういった教育は学校で普通教育としてやらせるべきであると考えているからです。しているところはしているでしょうが、全校に義務付けてほしいですね。
これは結果論でもなんでもなく最善手と言い切れる。理由は言うまでもなく二次災害の防止である。これに類似する事例はいくつもある、いわゆる善意や勇気が裏目に出るケースだ。
消防員が止めるのも聞かずに火災現場に救助しにいき消防員の手間を増やし救助を妨害してしまったり、池で溺れている人を助けようとして何故か自分も池に飛びこみ誰にも連絡されず死亡したり、せっかく岩清水八幡宮へ参拝しに行ったのに山までは行かずに帰ってきてしまったり。
さて、こういった悲劇が何故起こるかといえば適切な知識を有していないことが原因といえよう。
そこで今回は我々のような一般人が事故現場に居合わせた場合の適切な処置を出来るだけ最小限に圧縮して覚えておきたい。
色々な手順を書いても焦ったときに思い出せるかどうかは果てしなく疑問だ、できれば暇なときは自分が妄想の中で大活躍する話を想像して脳内物質を分泌するよりも、自分がこの場で何らかの事故が起こった場合どのように対処すればいいかをシミュレートしていた方が役に立つだろう。
まず最初にすべての事故に共通して言えること。
『周囲の安全を確認する』
重要なことなので滅多に使わないだろう色彩字を使って表現しました。
いの一番にこれを行ってください。じゃないと
『感電している人を助けようとして近づいたために自分も感電する』
『有害ガスを吸って倒れている人を助けようとして自分も(ry』
『毒へビに咬まれた人を助けようとして(ry』
『崖崩れで負傷した人を助けようとして(ry』
『道路の真ん中で倒れている人を(ry』
などなどこれを怠ったばかりに相手を助ける前に自分も要救助者になってしまったり死亡者の数を一つ増やすことになるので絶対に行ってください。
原則として要救助者を助けることよりもこれ以上要救助者を増やさないことです。
危ないと思って無我夢中で、というのはやらないでください。
よくニュースでこのような受け答えをする人がいますができるだけ避けるべきです。まずは冷静になって状況を把握しましょう。
『専門家に連絡する』
これも重要です。まずは自分でどうこうしようなどと考えずに年長者や経験者、特に消防や救助の方に連絡しましょう。自分ひとりしかいない場合なんて滅多にありません。
学校ならば教官に、職場ならば上司に、道端なら周囲の人に、そして救急車を呼びましょう。
工場や職場などではそこを担当している管理者は少なくとも貴方よりは適切な処置を事前に教習しているはずです。まずは連絡しましょう。どうせ1人ではできることはあまりありませんし何度も言いますが危険です。
あとその現場責任者や専門家の指示には絶対従ってください。言い合ってる間にも救助を待っています、
ところで、割と重要なことですが通報する際にどこにどう連絡すればよいか知っていますか?念のために確認しておきましょう。多分5割くらいの人間が知りません。
まず最初に「119」にダイヤルしましょう。
119です、これくらいは覚えて置いてください。
できれば携帯電話に登録しておいてください、そういえばこういった機能が付いた携帯はあるんでしょうか。念のために言っておきますがここで火事だ救急だと悩む必要はありません。とりあえず事故なら119です。
ダイヤルするとオペレーターが「火事ですか?救急ですか?」と尋ねてくるので答えてください。あとは多少慌てていてもオペレーターの質問や指示に冷静になって応えていれば大丈夫です。安心してください、餅は餅屋に、指示はオペレーターに。
言っておかなければならない連絡事項としては
・事故火災の住所(県名から言ってください。出来るだけ詳細に)
・怪我人病人の状態(どうやって怪我したか、現場の状況、症状や出血など)
・現場の目印になる建物など
・通報する人の名前
・救急車の来る場所
などです。念のために言っておきますが、正確に状況を伝えてください。主観で「○○だと思うのですが」などと言わなくていいです。
また、電話は相手が切るまではアクティブにしておいてください。もしかすると追加で指示があるかもしれません。
通報に使用した電話はすぐに出られる位置にいてください。また他の用途には使わず他への連絡は違う端末を使ってください。
あとは、救急車が近くまで来たら現場まで誘導する人を出してください。夜間なら照明を持っていくとGJです。
もしかすると症状によっては嘔吐物を調べる場合があるので可能ならばビニール袋などに保管しましょう。
最低でも1人は事情を知っている人が救急車に同乗することになります。
毒虫などによる場合はその毒虫を可能なら捕獲しましょう。
危険ならば写真を撮るか特徴を観察してください。
あとで血清を入れる際に特定しやすくなります。
(参考:東京消防署公式サイト)
これでも心配なら携帯で『通報マニュアル』と検索して出てきたページをブックマークしておきましょう。マニュアルは最善手です。
というわけでこの二つだけは覚えておきましょう。
もはや、覚えるとかそういうレベルじゃないですけどね。
『安全確認』と『通報』だけ覚えておけばなんとかなります。
下手に処置するよりもずっとファインプレーです。どうせ具体的に何かしなければいけないことがあってもオペレーターの人が教えてくれるはずです。
マニュアル通りの対応もできない人に柔軟な対応なんて無理です。
何故この記事を教育カテゴリで書いたのか。
それはこういった教育は学校で普通教育としてやらせるべきであると考えているからです。しているところはしているでしょうが、全校に義務付けてほしいですね。
PR
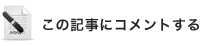
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(03/02)
(03/02)
(02/25)
(02/23)
(02/20)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
鶏冠(とさか)
性別:
男性
趣味:
Civilization3/4、mahjong
ブログ内検索
最古記事
P R
アクセス解析
カウンター
